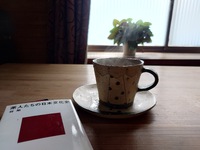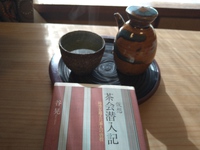2022年12月07日
秀長に学ぶべきところは多い
【秀長に学ぶべきところは多い】
12/7 goodmorning
朝から、#まちかど漫遊帖 事務局と長い長い打ち合わせ。大事なのは時代に沿った変化だよという話をする。20年近く前の慣例だけで動かそうとしても、ひとは動かない。
昨日、火曜日の #チームキャロル の稽古がすんだので、今日は午後から、11日の日曜日の茶室る庵の茶会の仕掛けをする予定。
まぁまぁ大きく動かすので、みんながいるうちにピアノを片付けとけばよかったなと思いつつ、昨日は、話さないといかん連絡事項が山盛りだったから、仕方あるまい。
#豊臣秀吉 が「数寄の心ある者は日本中国内はもとより唐国からもまかるべし」と10日間の予定で始めた、#北野大茶湯。
秀吉、利休はもちろん、公家だろうが百姓だろうが釜ひとつ持ってあつまれば茶屋を持てる画期的なエンターテイメント性溢れる茶会だったのだけど、
この時期に、肥後で大きな一揆が起こり、それが関白秀吉の逆鱗にふれ北野大茶湯は一日にして閉幕。
翌日、片付けが始まる中、秀吉の弟 大和大納言 #豊臣秀長 だけは、遠く奈良や大和からきておるものの為に、1日茶を振る舞ったそうで、なんとよくできた気遣い。
その2年後、その時の恩義に対し奈良衆が秀長のための茶会を開いたそうで、奈良大和のひとたちと秀長の関係が良好だったことがわかる。
秀長が亡くなったあと、秀吉と利休の関係もややこしくなり、豊臣家も衰退していくのは、こうしたひとがいなくなったからかも。
そこが「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と、言われる所以。
夕べの、るいまま組の会談も、大袈裟ではなくても、ひとを思いやる気持ちや、それを受け取る気持ちって大事だよなって話。
秀長に学ぶべきところは多い。

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。