2024年04月19日
その向こう側を
【その向こう側を】
「#工藝とは何か」。いよいよ最終章となった。赤木さん、堀畑さん、関口さんは、雨の奈良・#秋篠寺 で話をはじめる。ここには芸事の天女「伎藝天」がいる。

「うるし」という言葉は、しっとり水分を含む質感「うるおい」から来ている。「うるわしい」は生きているように潤いに満ちている。堀畑さんが「うるしの本質をついていますね」と言い、
続いて、「漆ってある意味、ウルシの木の血液じゃないですか。その血液を取られた木は死んでしまうんですよね?」と問うた言葉に、赤木さんが答える。
「死にはしないですね。苦しむでしょうけど」
ウルシの木の全身から血液を絞りとるように、ひと夏かけて樹液を採取する。最後は、根から梢の葉っぱまで通じている導管を切断し、木は枯れたように落葉を始める。
しかし、葉がすべて落ちる前にその木を切り倒すと、その切り株から同じ遺伝子を持った芽が吹き出して、15年~20年経つと立派な木になる。
そのサイクルの二番目のほうが良い漆となり、三番目はそれよりも良い。
たとえ木を切り倒しても根は生きていて広がっているから、根の先からも、また息吹く。
この生命力あふれる循環の話に「漆」の持つ力を知る。傷つけられた木は、自らを守るために樹液を流す。それには抗菌能力や抗ウイルス能力があり、硬化したあともその力は残る。
「漆の器は強くて軽くて抗菌能力もあって子どもたちの最初の食器にぴったりです」と私たちはよくアナウンスしていたが、
それはもちろんだが、命を繋いでいく力こそが、漆器を勧める理由にならなくてはいけない。単に道具としてだけではなく、漆が与えてくれたものと共に生きるという意味だ。
「工藝とは何か」を読み進むほどに、「用の美」を唱えた柳宗悦の民藝と、ここにある工藝は、やや違うのではないかと感じていた。
民藝という言葉には、生活のなかでつかわれる簡素で飾らないものや、ごつごつとしたものたちにある美を想像するが、工藝となると、それだけではないような気がする。
その思いの答えは350頁にでてくる。
民藝運動が始まる前、軽んじられていた「下手もの」にも美が宿っていることをことさら強調したがために、民藝は「下手の美」に限定されてしまった。
社会が変化し信仰の失われた時代となり、民藝は根幹となるものを失った。
そして、民藝思想が生まれた20世紀前半から抜け出せておらず、「日本民藝館のようなごつい和風の空間と親和性を持つ器物が民藝」と思われている。
時代を変えるほど革新的なものは、根強い信奉者も多く、そのぶん軽やかさを失う。どんなことも変化しながら進みいかねば古びてしまう。
しかし、背骨となるものがないまま変化だけをのぞむと、わけのわからぬ浮遊物になってしまう。
それは、たぶん工藝に限らず、どんな分野でもだ。
「工藝っていうのは、たんに生活のなかで現世利益的に役立つ、便利で手作りの自然素材の道具をつくることだけではない。(表面的に同じに見えても)見えないもの、その世界の背後にあるもの、あるいは背中合わせになっているものを探求する。そこを目指しているんです」
と語る赤木さんの言葉を、私は100円ショップの器だって使えると言われ苦しい思いをしたと話してくれた若い漆芸家に伝えたいと思う。
「手にのせられて、膝で抱えられるような小さな器であるけれど、それは茶室とか、お座敷とか、床の間とか、炉とかと同じような象徴的な意味を持っている。そこを転換点にして、世界がぐるっと入れ替わるみたいな、そういうもの。であるからこそ、ほんらいの力を持てるんじゃないかと思うんです」
赤木さんのこの言葉で、長い「工藝とは何か」の旅は終わった。
………
コロナが始まる前と後で、世界は変わったと私は思っている。時間に追われるように進むときに重宝されたのは、簡単でわかりやすく安価なものだった。忙しくて、とてもゆっくり考えてられないと思う人が多かったからだと思う。
いざ、時間ができてしまうと、その簡単で大量のとりあえずのものたちが自分に襲い来ることにきづいた。それは、道具だけではない。社会もひとも。
オセロのように、いろんなものがひっくり返っている。塗り固められた美しかったものの外壁が壊れ膿がでたように、
堅苦しく難しいと目をそらしていたものの向こう側にある、親しみある優しさや、嘘のない世界に気づくひとが増えますように。
2024年04月18日
希望の工藝
【白磁する】
#黒田泰蔵の円筒 を集めた特別展が大阪 #東洋陶磁美術館 で開催されたのは2020年秋から翌年にかけてだ。
https://www.moco.or.jp/exhibition/past/?e=565
ちょうどコロナが広がり、だれもが見えない恐怖の中にいた頃だ。黒田泰蔵は、この特別展の途中2021年4月に亡くなる
#工藝とは何か。も、いよいよ 六章 #工藝の原點 まできた。
この章は、黒田泰蔵の「円筒」から始まる。
赤木さんも、堀畑さんも、工藝の原点はなんだと観念的に哲学的に、原田老師の言葉や黒田泰蔵の言葉を何度も反芻咀嚼しながら考えていく。
黒田泰蔵展をみた陶芸家の #高木逸夫 さんが、「観ているうちに吐きそうになった」といった話が引用されている。
気分が悪いという意味ではなく、
「(あれを轆轤で挽くために)、とてつもないエネルギーが必要。低速、高トルクで、あれひとつつくるためにいったい何キロを、指と指の間で回転させていなければならないのかを想像したとき、吐き気がしてきた」
その凄まじい労力の果にも完璧はない。
そして303頁、ふたりと関口真紀子さんは、主のいなくなった黒田泰蔵のアトリエに向かう。
黒田さんがいなくなり寂しい場所になってはいないかと杞憂していたが、そこは「空間がいきいきして、黒田さんがいつあらわれてもいいような感じ」
黒田さんは自身が作った小さな白磁のなかに、黒田さんは入っていた。
「だんだん肉体が亡んでいく過程で、縮んで小さくなっていく姿がそこにあって、最期「すっ」とそのなかに入っていかれた感じで」と赤木さん。
関口さんは、
「なんか美しい形なんだけど、緊張感でこちらも緊張するような形ではなく、どこか穏やかさ、柔らかさというようなものを、閑さと。形はシャープなのに、緊張させられない」
「黒田さんのひとそのものが滲み出ているような。「円筒」という形は、観念的で抽象的なものだと思うんですが、最期の円筒は愛らしい感じがしました。慈愛に満ちている感じ」それが親しみに繋がっていると、堀畑さん。
黒田泰蔵の使っていた「#白磁する」という言葉は、絶対無であり空であり、有も無も包み込むよなゼロ。
黒田さんは、自分が最も白磁していたのは皿洗いをしていたときで、皿洗いという同じ動作をやり続けているとき「#自分が消えていく感じが気持ちいい」と言った。
黒田にとっては、指と指の間で果てない距離を回転させていくのは、人生の問題を解決するためのひとつの方法だった。
何事も小賢しく考えるよりも、赤木さんの言っていた「感謝と祈り」に工藝の本質があるんじゃないかと堀畑さんが言うと、
赤木「僕も口で言うほどにはわかっていない。小賢しい近代的自我を持ってしまって」
堀畑「しかも、哲学的に考えてしまうという、一種の病がある」
というやりとりには、吹き出してしまった(笑)
たくさんの人と悦びを分かち合うというのは、言葉にすれば難しいが、何も特別なことではなく、今までの歴史のなかで誰もがそうやって人の輪をつくり、生きてきたと堀畑さんが言い、
赤木さんの「希望の工藝ですね」
とこの章は終わる。
黒田泰蔵が残した、無駄のすべてを削ぎ落としたようは円筒は、ひとを寄せ付けない鋭さの向こう側に、苦しい時間を乗り越え、自我をすてたからこそ見えた希望の光がある。
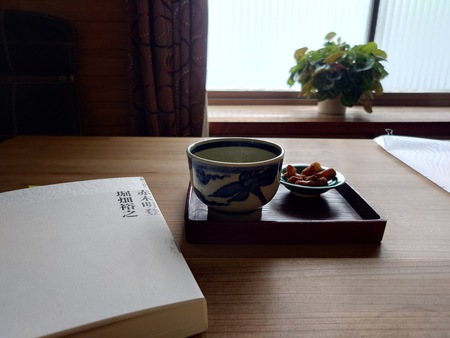
2024年04月17日
愛すべきもの
【愛すべきもの】
#工藝とは何か。#ピンブロウ 硝子作家 #艸田正樹 さんと #赤木明登 さんの対話は、最初からすうっと入ってきた。

街づくり系のシンクタンクに勤めていた艸田さんは、休みの日に場を開放している下町の硝子工場に気軽な気持ちで行ってみる。
そこは、趣味の硝子教室というより、大学で勉強したひととか、ステンドガラス作家とか、誰かに教えてもらわなくても作れるひとばかり。
艸田さんは、工場の職人さんから「プロになる気はないんだね?」ときかれ、「会社員だからぜんぜんないです」と答え、「じゃひとりで作れる方法があるから」と、ピンブロウを教えてもらう。
ピンブロウは、私たちが思う吹き硝子ではない。パイプではなく鉄の棒の先にガラスを巻き、竿の反対側に小さな穴を開け、濡らした新聞紙で塞ぐと、水蒸気がでてガラスが膨らむ。
「いつか上手にできて、それでお酒でも飲めたらな」くらいの気持ちで始めたピンブロウにハマり、20年以上。今も、その気持ちはつづいている。
2年ほど、月に一度くらいのペースで硝子工場に通っていたが、会社に入社して3年目くらいから忙しくなり、硝子工場に通えなくなる。
そして5年目、自分に限界を感じ会社を辞める。その時、30歳。
会社を辞めてからの艸田さんが良い!
便利さや情報を遮断し、雪の重みで茅葺きの屋根が潰れるほど雪深い町 富山県八尾で「ひと冬過ごし、今後の結論をだそう」と暮らし始める。結局、5年をそこで過ごす。
赤木さんが、その5年何をやってたんですか?と問うと、
たまたま出会った富山の硝子教室で「ピンブロウだけできるんでやらせてください」と、ひとりで硝子を作り始める。
「やってみたら、またすごい気持ちがいいんです」
艸田さんは、師匠を持たない作家だ。自分でやってみて少しずつ進む。
溶鉱炉のなかは1000度から1200度。すごい炎に向き合わないといけない。危ないので気を抜くことはできず集中する。
「それが滝に打たれるような感覚になり、雑念が飛び、あれこれ考えなくなって、#いまあるこの瞬間だけになる」
でてくる硝子の透明が、自分に染み付いていたいろいろなものをリセットしたいという思いと感覚的、連想的に近かったと艸田さん。
「最終的にこういう形にしようというのはないんですか?」と赤木さんが聞いた。
「ないんです」
艸田さんの言葉を読み進めると、同じようにやっていても予定通りにいくわけではないことがわかる。
そんなときは、硝子に無理をさせない、硝子の言葉をきく、そして生まれたものは
「自分がデザインしたものではないけでど、きれいなものがあらわれた」というのが、
#いまつくる行為のなかのリアルな形。
「匠の技でものを仕上げるんじゃなく、自然現象の組み合わせでつくる器の形。人工の工藝品のうつくしさというより、自然界にあるもののきれいさが、ここにあらわれてくれれば、それが僕にとっていいもの」
艸田さんが前職から離れたほんとうの理由はわからないが、私自身、長くいろんな町を取材しながら思うのは、
美しく仕上げられた理想の都市計画やまちづくりの理念は、プレゼンの場では絶賛されるが、
実際、その街を歩けば、図面や計画のなかから削り取られた部分が見えてくる。
現実的なものは美しくはないかもしれないけれど、息づく町の姿だ。
夢のような机上の論ばっかり語る会議は嫌いだ。
そうしたものは流行りや他者の圧力によってずれていく。
大事なのは、いまここにある現実だ。
どうしようもない現実のなかに現れる「愛すべきもの」をすくい上げる。
艸田さんは、たぶん私よりずっとずっと若いけれど、それを知っているのだろうと思いながら5章を読み終えた。
2024年04月12日
言葉は消えても
【言葉は消えても】
「工藝とは何か」。私が最も迷い道に入っている、赤木さんと荒谷さんの対話「#民藝の核心」の章も最終項にはいってきた。

赤木さんは、森を歩くとき、それが波のように見えると言う。
森は「土のなかから芽が出てきて何かが膨らんで光を求めて上にどんどん伸びていって、夏の終わりには水分を失って枯れて萎んでいって、そして葉を落として木は倒れて腐って土に戻っていく」
それは全く波と同じ。
縄文人は、この森のなかに生き、この波がごとく繰り返される事象のなかに自分自身もいたことを自覚していた。
#縄文土器 は「森のなかで生きてきた人々に、生まれながらにして備わっている感覚をイメージ化したものだと思えるんです」と赤木さん。
言語で表現するずっと以前のことを語るとき、それは「宗教」なのか「神秘」なのか「霊性」なのか、赤木さんも荒谷さんも決めかねている対話が繰り返され、
赤木さんの言った一言が、とても印象深い。
「…一種の「#愛」だと思う。言葉にもできないし、得体も知れないけど、とてつもなく魅力的なものがあって、そこに目をこらして、何かをこちら側に持ってきたいという欲望」
漆には、漆が本来なりたい方向があり、それを損なわず、人為的に抑えることなく引き出してやる。それが漆が持っている「ほんらいのありよう」。
これを読みつつ #ほんらいのありよう から外れたときの崩壊を人間は何度もくりかし、すでにわかっているのに、また同じことをやってしまう。
愚かと言えば愚かだが、近代化とか最新鋭とか革新という言葉に塗りかためられ、支配された社会から抜け出すことができないのかもしれないなと感じた。
とはいえ、ならば全てがゼロポイントのことであれば、全ては美しく愛に満ち無心と言えるのかと言えば、それだけでは進まぬものもある。
ただ、目的を決め作為的にやることを経るとしても、繰り返される「#膨大な単調」のなかで忘我の境地になる。
赤木さんは、ギリギリのところで向こう側に「#寄り添う」と言う。
寄り添うとは「ほんとうに何もない無心でも、直観でもなくて、言語化され尽くし、計算され尽くしたこの世界のギリギリのところに行って、さらにその向こうにある言語化できないところにアプローチする。そこは「無心の心」というより「諦め」に近い。手も足も出ない」
柳宗悦は、工藝を探究し語り尽くしたわけではなく、出会いが遅くやり残したことがあり、それが縄文だと言い残しているようだ。
理論や言葉では説明のつかない「#超越的な自然と人間の関係から生まれた工藝」
「言葉は消えても縄文の記憶は、土器みたいな工藝品に具現化されてそのまま遺っている。そこには言語意識によって埋め尽くされる前の、もっと古い意識が地層のようにあらわれていて、そこを掘り起こせば何かが出てくるんじゃないかと思っています。
#日本の縄文はすごいんですよ」
赤木さんのこの「日本の」は強く響いた。
東洋人いや日本人は、あまりに西洋至上主義に毒され、本来の自己の誇りを失っている。
先日来書いていた「花子を探しています」の資料読みの中で、明治時代、日本では、ヨーロッパを巡業する芸者あがりの旅芸人などと言われていた花子が、
当時、近代演劇の先進国と言われていたモスクワ芸術座で、居並ぶ名優や学生を前に、自分が観て育った日本の伝統文化から作り上げた自分の芸を演じみせ、近代演劇の意識まで変えさせた話は、
言葉もわからぬ未知の世界で作為も加えず、ただ自身の有り様だけで生きた女性の強さに感動したのだが、
言葉なき世界は、なんとも強く美しく逞しいことよ。
と、言うわけで、難航した 四章「民藝の核心」を読み終える。
2024年04月11日
言葉という道具
【言葉という道具】
「工藝とは何か」。赤木さん、荒谷さんの #柳宗悦 との出会いあたりから、なかなか理解し辛くなってきた。
しかし、読み進むうちに、最早「言葉で理解する」というところには無いのだと気付かされる。
読み取ってやろうとか、理解しようとか、意識的に動くほどに迷い道にはいる。
荒谷さんは、柳は美というものを、ただの感覚としてではなく、宗教的な理念として考えていたように思うと言う。
「#柳が求める真実の美 は、とらわれのない「心のありよう」。これは、知識や分別を捨て去らなくては感じられず、柳が知識ではなく「直観」でみなければいけないと繰り返し説くのは、そういう理由」
直感ではなく、直観を使うのは、野性的なものではなく、本質を見よということだと、私は理解しながら、さらに読む。
「(私たちは)ふだん、言語意識で分別された世界に生きている。あるものを「美しい」と言うとき、すでに「美しくない」ものと区別している。「私」と言えるのは、「私以外」があるから」
分けることができる #二元の世界。仏教では、こうした 分別意識が苦しみの原因 と考えられるのだと荒谷さん。
「柳が探究したのは、そういう二元意識が滅した、あるいは生まれる前の #主客未分の状態」
「(夢よりももっと深い) 非二次元的な意識は、言葉や、言葉と密接に結びついた自意識が滅した意識の極点」
宗教でさえも人間が作ったものであり、語る人間がいたのであるから、それをも取り払った宗教の土台とも言える #無色透明な意識のゼロポイント であると、この項は結ぶ。
言葉を生業にし、まやかしを繰り広げ、細々と生きる者にとって、なんとも苦しい話ではあるけれど、
実際のところ、言葉の無意味さ怖さを感じることは多い。
赤木さんも書いていたが、言葉というのは「便利な道具」で、いかようにも使える。
使えるがばかりに、重ねすぎて本質を覆ったり、捻じ曲げたり、色まで変えたりと危険な一面も持つ。
言葉を重ね見失うものがあることを「そんなものどっちでもええねん」と思えるだけ肝が座れば生きやすくなるのかもしれないが、
言葉に支配された人間(私)は、なにかと言葉で説明をつけようとして、無色透明な世界から遠ざかる。あぁ、早くこの項から抜け出したい。
…と思いながら、柳宗悦にしても、荒谷さんにしても、言葉によって無色透明なる世界を表現することに苦しさを感じたことはないのだろうか?
と今朝は本を閉じる。

2024年04月09日
心の本然を理解する
【心の本然を理解する】
「工藝とは何か」を読む。
今朝は、京都で工藝ギャラリーを営む #荒谷啓一 さんと 赤木さん。
荒谷さんは、7年間チベット寺院で修行をしたのち、タイに渡り12年を過ごし日本に帰ってきた。
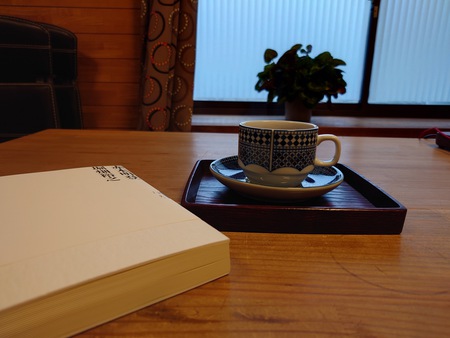
赤木さんが、修行というのは悟りを開くためですよね?と聞くと、荒谷さんは「悟りは開いていませんが、得難い素晴らしい経験」だったと答える。
悟り自体は目に見えるものではないが、心のきよらかさは外見にも出てくる。ひととの接し方、佇まいなど、全てにおいて #優しさと晴朗さがあふれている。
悟ったひとは、自分が悟っているなんて言わない。日本は「#悟り」という言葉の宗教臭が強すぎると、荒谷さん。
「(チベット)では、「#心の本然を理解する」という意味です。先生もふつうの人間です。でも、なんでもないふつうの人が、そういう状態に達成しているということが人間のすごさかなって思います」
赤木さんの、チベット仏教の根底にある永遠に続く「#不滅の魂」について問う。荒谷さんは、「#心の連続性」と答える。
「死んだら終わりではなく、生前のカルマによって別のものに生まれ変わるという考えは、死への無意味な恐れをなくし、いま与えられている人生をより良く生きようという動機になっています」
これを読みながら、日本でも、修行僧でもなんでもない普通のひとたちが、あれはな××さんの生まれ変わりや。あんたを守ってくれてるんやでと口にすることは、のどかなる嘘ではなく、古代から続く自然の死生観だったんだろうなと思った。
神様も仏さまも突き詰めればひとつ。そのひとの心のなかにあるものだと、最近とみに思う。
話が進み、柳宗悦のやりたかったことは何か?になる。私は、ここでひとつの答え合わせに出会う。
柳宗悦は若い頃ロダンに傾倒し探究していたという。
「ロダンにとって、自然はそれ自体、完全なもので、神と同一のものでした。「自然 宗教性 藝術」がロダンのなかでは繋がっていて、そこに柳も共感したのだと思う」
いま、書いている「#花子を探しています」の中でロダンは重要な役どころだが、花子が女性モデルというだけでゴシップ的な視点でしか見ないひとが多いことにがっかりしていた。
ロダンは、ロイ・フラーに勧められ初めて花子を観たとき、日本人女性が演じる死の表情に大きく心ゆさぶられる。それをうつしとりたいというロダンの強い思いの根底にあったものは、ここだったのか。
2024年04月08日
行動する命
【行動する命】
「#工藝とは何か」を読み進む。

第三章は、塗師 赤木明登さん、服飾デザイナー堀畑裕之さんの様々な質問に、原田正道老師が禅の世界から解説しながら、話は進む。
同じゴールでも、自分の中にゴールを見つけるが禅宗だという老師に堀畑さんが #ゴールとは何か ときく。
「「行動する命」そのものを見つめることです。食べる、座る、歩く、仕事をする。すべての「行動する自己」を見つめること。たとえば、何かを見るとすると、その見ることを見るのです」
禅の目的は悟りなんでしょうか?
「悟りとは、そんなに難しいことではないのです。誰でもわかってしまえば、常にそれを感じながら生きられます」
「認識を離すということが一番大切です。「空っぽ」というイメージを自分で作って、「空っぽ」のイメージに自分がなりきるとい、その工夫をするしかないんです」
「呼吸というものは、意識すると複雑になります。繰り返し繰り返しやっていくなかで自分の呼吸の状態を、自分で工夫していく。こういうことが大切です」
赤木さんの、ふつう坐禅というのは「考えないこと」をもとめられられるようなイメージなんですけど、と言う質問に、
「でも「考えない」と言うて「考える」ならば、それは大きな障害になる。#繰り返しやっているうちに考えなくなってくるんです。これはもう習慣性です。考える習慣をもっている私たちが、そうなろうとしてもムリです」
そんな対話のなかで、赤木さんは、
職人として同じお椀をひと月に三百個くらい作り続ける暮らしを1年間続け、それを30年やっているので一万個単位のお椀を延々とくるようになった。
最初は、自分の意志で椀をつくっていたような気がしていたけれど、お椀のほうが意思をを持って、自分を使って勝手に増えているような感じになってきた。
その時の自分が「空っぽのパイプ」となり、お椀が自分の中を流れていくような心境になったと話す。
「#それが坐禅なんです。坐禅というかたちを想念されるからおかしい。そうではなくて、毎日の暮らしのなかに、繰り返していることのなかに、坐禅があるんです」
嫌な仕事を「やれ」と言われれば、そりゃ嫌だけれど、ただ続けるだけ、ただ歩くだけ。そのうちみつける「リズム」によっていくらでも続けられる。
そして、赤木さんは、大先輩の職人さんが言っていた「#数をこなすと見えてくる世界がある」こそが禅の悟りの境地に近いものであることに気づく。
この章は、先日読んだものの、一向に身体にはいってこなかった #典座教訓 の解説書のようだ。
茶席によく掛けられる「無」やら「空」やら「円相」、もっともらしく話をするひとがいるが、もうそれは説明できないもの、そう言うより仕方ないものだという老師になるほどと思う。
「個々がそれぞれ生き、努力してきたから、それが現れただけのこと。だから「空」という世界が存在するはずがない。
けれど全体をとらえて言うならば、あらゆる試行錯誤、失敗したり、成功したり、それらすべてを全部その表現のなかに、納めることができる。
ここのところを、よくよくご覧になれば「空」という世界に騙される必要はない」
机上の考えやら、もっともらしい話に騙されない、自ら行動して掴むひとになれますように。
■茶人
何も考えない。
そんな時間は、素敵ですけど、時々時間を無駄にしていないか?と不安になる事もあります。僕は何も心配しない生き方をしているので、何が起こっても反射的に答えが出せますけど、正しいかどうかは別問題です。わけのわからん人生ですね。
若い人は、いろいろと心配して、過呼吸になったりする人も多い。
出来るだけ息を吐き出せば、自然に入ってくるのにね。
■るいまま
そうそう。吐けば吸えるのにね(笑)
けどま、若い頃、過呼吸に悩まされた身としては、ここに来るまで苦しいこともありましたから(笑)
■茶人
るいままでもそんな時期があったんですか?意外ですね!
■るいまま
だから、私は兄の病気がきっかけで、ひきこもっていた時期に茶を押し付けられ、社会を全部敵にまわしていた、HSP(Highly Sensitive Person)
ハイリー・センシティブ・パーソンですよ(笑)
HSPってなんだったっけ?って聞いてくると思うから、はりつけとくよ(笑)
http://www.madreclinic.jp/pm-top/pm-symptom/pm-symptom-22/
■茶人
まぁ、僕も基本的にはかなりの引きこもりですから、繊細な頃はあったような気がします。人が苦手。
■るいまま
ひとり行動が好きなのは、どうしても合わしてしまう傾向にあるので、ものすごく疲れるんです。相手がどんなにいい人でも、私側の問題として。
だから、小説を書くというのは、私自身の心の整理のためであったと思うのです。
2024年04月06日
漆器は自分の手のように扱う
【自分の手のように】
今朝は、赤木明登さんと、曹源寺老師 #原田正道 さん。

岡山の禅寺 曹源寺の原田さんの名前は、別の方から教えられていた。道元のことは、あれこれ難しく考えず典座教訓を繰り返し読むことを勧められたと、そのひとは言った。
典座とは、禅宗寺院で仏への供膳とともに修行僧の食事を調える役職。
輪島の塗師である赤木さんと、修行した寺で何千何百の漆器を扱ってきた老師の話はすすむ。
「漆の良いところは、触ったときの感覚が人間の皮膚に近いところなんです」と赤木さんは言う。自分の手を扱うように漆器も扱えばよいだけ。
手をタワシやクレンザーであらったり、電子レンジや乾燥機にはいれない。そして、洗えば拭く。
漆器をみてプラスティックのように見えるというひとに、まず目を瞑り触ってもらう。何を感じるかときくと、「柔らかい、あたたかい」という。
漆は硬化すると、とても強い炭素でできた膜になり酸にもアルカリにも強くなる。何千年土の中に埋もれても腐らない。
それでも、人間は「柔らかい、あたたかい」と感じる。
それは膜のなかにたくさんの穴があり、そこに水分が入り込んで一定の水分を含んでいるからで、とても繊細な人間の皮膚は、それを感じとれるから。
この水分「潤い」を与えるのが「人間が使うという営み」。
つまりは、漆器は漆器だけ置いていても寂しくなってしまう。ひとと共にあっての漆器なのだ。
ふたりは、このあと 心のありようについて語る。
それはまた次に。
2024年04月05日
工藝と工芸の違い
【工藝と工芸】
今朝は、赤木明登さんと、服飾デザイナー #堀畑裕之 の対話。

少女茶人だった頃、私は先生と二人きりで、自宅の和室に粗末な道具を広げて稽古をしていたので、本物をみることがないままだった自分を卑下していた。
だが、この章を読みながら、なぜかとても励まされたのだ。
先生は、未熟な私が点てた茶の碗であっても、いつも両手で捧げ持ち頭を下げてから茶を服す。
当たり前のことだと思っていたので、茶を長く長く離れ、久々に茶席に呼ばれたとき、そうしていると、そこにはまるで違う世界があった。
茶碗を右に置いて礼、左に置いて礼、自分の前に置いて礼、うちにいれて礼。ぴょこぴょこ頭を下げるうちに茶はどんどん冷めていく。
そのあまりに形骸化された、謎の礼だらけ作法に馴染めないまま今に至る。
そして、遠い昔、12歳の私にも敬意を払っていてくれていた先生から伝えられた「礼を尽くす」を思う。
私は先生を受け入れない反抗的な少女だったし、上手に点った茶ばかりではないのに、必ず捧げ持ち、点前座にいる私に静かに頭を下げ一服一服いただく。
あれほど気持ちのこもった「いただきます」はない。
さて、この対話の中で、もっとも心に残ったのは、やはり「藝」と「芸」の文字の成り立ちの違いだ。
「藝」は、神様が降りてくる場所に木を植えている図。訓読みは「うえる」。
「芸」は、真逆の意味で、訓読みは「くさきる」。
だから、「工藝」を語るとき「藝」を使う。
「自然から恵みをいただいて、大切に育て、未来に繋げていくことは、この「藝」のほうがピタッとくる」と堀畑さんが言い、
赤木さんも、それを意識して、書くのは大変だけど「藝」を使っていますと語る。
2024年04月04日
ふつうって何だろう
【ふつうって何だろう】
赤木明登さんと 陶芸家 #黒田泰蔵 との対話を読む。

一時期アバンギャルドの象徴的な作品を作っていた黒田泰蔵が「ふつうのものをつくりたい」と思った瞬間、
ふつうってなんだろう
#個性にどれだけの意味があるんだろう
個性的なものをつくりたい人がいるけど、それは変わったものをつくりたいだけじゃないの
と、考え悩む。
「個性というものを消していったら、僕のほんとうの本質がでてきて、人間が持っている個性みたいなものがあるんじゃないかと、それがホントの個性なんじゃないかな。」
そこから、人間の個性みたいなものを消し、哺乳類の個性みたいなことを消したら、最後に残るのは宇宙の個性…それが真実ではないか?
この章の最後に、柳宗悦の言葉を引用解説した一文がある。
「浄土はどこにあるのか。この世界の彼方の、どこか遠く、別の場所にあるのか。そうではない。浄土とは、いまここにある。
ありふれた日常の傍らに、目の前の自然のそのただなかに、いまもある。
そこにあるものをぼくたちは、#ただ見失っているだけなのだ」





