2025年03月30日
狂言の3つの柱は、小舞、狂言、語り
【狂言】
狂言の3つの柱は、小舞、狂言、語り。
語りは、
「言葉による表現が中心となる狂言において、「語り(かたり)」は大変重要な芸です。これは、情景や合戦の様子などを身振りを交えて語るものです。普通のせりふまわしとは異なり、息の流れを生かして緩急を付けながら、迫力をもって表現します。『文蔵(ぶんぞう)』『朝比奈(あさいな)』の曲中に用いられるほか、能の間(あい)狂言、特に「語リ間(かたりあい)」において多く聴くことができます。」
狂言ではないが、語りを担うものとして、美しくサラサラやらないことを旨に稽古中。
こちらのyoutubeは、小舞、狂言、語りの差がよくわかるので貼り付けとく。語り「奈須与市語」しらなかったけど、いいね。
茶室演劇としてリライトして復活予定の「悩める与一」の参考になるわ。
小舞「七つの子」、狂言「鐘の音」、語「奈須与市語」
https://youtu.be/pkyRKn9l3Xw?si=TtCRNydgl-YwPLQi

2025年01月29日
狂言師 茂山千五郎!に稽古をつけてもらった!
【茂山千五郎!】
今日は、夕方から園代さんと岡山 #蔭凉寺 へ。
ここで狂言大倉流 #茂山千五郎 さんのお稽古があったのです。
園代さんが、奈良東大寺で千五郎さんと共演したとき、「えー。私、茂山千五郎家の追っかけなんですよ!」と話していたのを覚えていてくれての今回。ありがとう!
いつも、舞台やスタジオの向こうでみる千五郎さんを間近にみることができて学ぶべきこと多し。
単発のワークショップではなく、ちゃんと入門してお稽古を受けるので、集まっているみなさんもしっかりしてらっしゃる。
岡山は、後楽園に能舞台がありますので、昼は、そちらでお稽古していたそう。
初心者でもわかりやすく、大好きな演目「柿山伏」「蚊相撲」を、千五郎さんがお弟子さんたちに指導する様子をみせていただき、舞台の使い方など参考になる!
そして、なんと、園代さんとワタクシも、口伝で「柑子」の語りの稽古をつけてくださることに。
私が主人で、園代さんが太郎冠者。
千五郎さんが台詞を割って語るあとについて語ります。
私は、一応普段から舞台で演じておりますので声だけは大きいのですが、園代さんの太郎冠者は俊寛島流しのところで節のついた台詞があり難しい。でも、そこはさすがの木村園代!
たっぷり最後まで稽古をつけていただき、ありがとうございました!
私たちのあとは、男性ふたりが、4月に舞台にかける「仏師」のお稽古。この演目は繰り返しの妙が、おかしくてゲラゲラ笑ってしまった(笑)。
稽古のあと、千五郎さんから狂言のお話。
初期の狂言は台詞が舞台ごとに変化したりアドリブがあったりのライブ感満載であったこと。口伝によって繋いでいったので書物として残っていてもあらすじだけ。
江戸時代になってからようやく、のちに残る形になっていったこと。残っているものでも、社会情勢や差別の問題で、今の世での上演は難しくなっているものがあったり、時代によって変化したりしていること。
見学で、こんなに手厚く教えていただけるとは!
いまは、入門して通うことは難しいので涙をのみますが、これからも茂山千五郎家の狂言は追いかけます!










みなさんの発表会は、6月22日 後楽園 能舞台で開催。
■柑子あらすじ
「前夜の宴会に主人のお供をした召使い(太郎冠者)、その時主人から預かった土産「三つ成りの柑子」を持ってくるように云われますが、すでに内緒で食べ尽くしています。困った召使いはあれこれと言い訳をはじめ、果ては平家物語に登場する俊寛僧都の島流し話まで持ち出して・・・(共同狂言社より)」
……………
■わ芝居~その参「サヨウナラバ」大阪公演 狂言ver.
2025年02月20日(木曜日)14:30
大阪 山本能楽堂 2/21(金)〜24(月祝)
https://kyotokyogen.com/schedule/20250220sayounaraba/
■逸青会 京都 16時の部
2025年03月08日(土曜日)16:00
京都 金剛能楽堂
https://kyotokyogen.com/schedule/20250308isseikai2/
■古典と遊ぶ 春爛漫茂山狂言会 お豆腐狂言会【ポイント】
2025年04月06日(日曜日)15:30
兵庫 兵庫県立芸術文化センター 阪急 中ホール
2025年03月08日(土曜日)16:00
京都 金剛能楽堂
https://kyotokyogen.com/schedule/20250406haruranman2/
2025年01月09日
全天候型 能楽堂ほしい
【福井】
1/9 goodmorning
福井市のハピリンホール(HappyとRingの造語らしい)は、屋根まである能舞台に変身できるのね。素晴らしい!
多目的ホールに、全天候型の能舞台が組めたら、もっと能狂言が身近になるかもなぁと思うんだが、高松には適当な大きさのホールがないよなぁ。
グランドホールでは、大きすぎるんだよ。
https://www.happiring.com/sp/floor/detail.php?cd=27
サンダーバードでメニエールが暴れ、仕事だからと泣きながら通った福井旅の思い出も今は昔。
再開発前の福井市駅周辺は寂しい感じだったけど、きれいに整備され、ホテルも増え、立ち消えになるんじゃないかと心配してた新幹線も通ったもんなぁ。
新幹線、京都までのびてくれるの待ってるよ!

■蘊蓄ギタリスト
能舞台に変身しなくても良いと思うのです。
能舞台のままで。ただ能狂言の風習がすこしだけ 西洋音楽にも歩み寄っていただいて
舞台に上がるのに 白足袋以外の新履物 すこしヒールがあって板をいためない柔らかい履物を考案して許可してくれれは
ヨーロッパの演奏家たちも 無味乾燥の日本多目的トイレちゃうホールよりも 能舞台を選ぶにきまってます。
金剛さんの舞台では新作やベートーヴェンを何度が演奏させてもらいました。ほんと 気持ちがいいです(笑)
やんなくても良いのに若い方に揚げ幕をサッとあけでもらって快感。ただ橋掛かりを歩むのが地獄。
めちゃくちゃぎこちなくて落ちそうになります。
多目的よりも・・・能舞台だけを作ればよいのに・・・と いつも思ってます。金剛さんの会館も演目の前はヨーロッパのオペラ座の雰囲気があります。
履物の問題だけですね。
靴を履かずに演奏をすると裸でいるような気がするのです。
■るいまま
福井市のホールが絶対良いとは思っていないけれど、能舞台を持たない県は、仮なりとも屋根や橋のある舞台で能狂言をみたいと思うよ。
薪能すら長く実施できていなかった県は、ようやく薪能を復活した日、雨に見舞われ、ホールに代替えの場所は準備しているときいていたけれど、能楽師さんや狂言師さんたちは山を借景とした野外を選び中止にはしなかったことに、私は感謝しかない。
福井のホールも、お客様はいつもとかわらない座席ではあるけれど、やっぱり、だだっ広いホールでやるのとは違うと思う。
大阪の大槻能楽堂も、室内の屋根付き能楽堂ではあるけれど、気持ちは高鳴る。
身近に能楽堂や、多種多様な会場があるひとは、個としての会場をと思うのは当然のこと。
地方においては、それが簡単には叶わず、ましてや自ら能楽堂を壊した(修繕という道は選ばなかった)地域性があるところに、いくら能楽熱が高まっても、それをいうのは詮無いこと。
■かおりさん
岡山のRSK山陽放送は
社屋に能楽堂があって神✨
こじんまりしとても素敵な能楽堂でした。
ここは舞台靴オッケーみたいですね。
香川の企業にもそんな心意気の経営者生まれないかなぁ^ ^
https://tenjin9rsk.jp/
■るいまま
岡本太郎の壁画があるところだよね? そういうところが率先して文化を高めてほしいねぇ。
ヒノキは傷がつくっていうから、靴の時はなにか敷くのかな? 敷くと響きが変わるので音響いれないといけなくなるのかも。
2025年01月03日
初笑い 茂山千五郎家「止動方角」
【初笑い】
正月3日朝、テレビをつけたら思いがけず 贔屓の 狂言 #茂山千五郎家「止動方角」。
馬 逃げた!
相変わらずキレがいいねぇ! 笑った笑った(笑)
主人・千五郎、太郎冠者・茂。馬は誰かしらん。





…………
■止動方角 あらすじ
茶比べに行くことになった主人だが、一切道具を持っていないので、太郎冠者に命じ、伯父の所へ借りに使わします。お茶から太刀・馬まで借りてくるように言われた太郎冠者は、伯父の所で全て借りますが、借りた馬が曲者で「後ろで咳をしたら暴れ出す」とのこと。
不機嫌に帰って来る太郎冠者を主人が遅いと迎えに行きます。散々に叱られた太郎冠者は、馬の後ろで咳をして、主人を馬から落としてしまいます。二度も馬から落ちた主人は「もう馬には乗らない」と言い、太郎冠者が乗って行くことになり、そこから太郎冠者の反撃が始まります。
よく、狂言は目下の者が目上の者を馬鹿にする、下克上の思想があるといわれますが、まさにそれを描いた作品です。また、「茶比べ」とは、中世に流行した遊びで、聞茶で銘柄や産地などを当てる遊びです。
2023年08月27日
さすがの熟睡!(笑)
【熟睡しました】
8/27 goodmorning
さすがに、頑固な不眠症持ちであっても、
朝5:30に起きて、掃除してシャワー浴びてから西宮までいき、
西宮界隈のさんぽのあと 茂山千五郎家の狂言をみて、
高松に帰ってきて、石あかりロードで ちんねんたちのライブをみたり、石あかりロードをさんぽしたり、実行委員会のじいちゃんチームと遊んだりして、
片付けをてつだって22:30。
で、帰ってきて、いろいろやっていたら0:30。
風呂にはいって、いつもどおりにベッドにのはいったあとの記憶がないくらい熟睡(笑)
めでたし!
写真は、狂言 茂山千五郎家のご贔屓の絵姿。これ書いた山本画伯は、ほんとに千五郎家好きなんだなぁと思う仕上がり。

2023年08月26日
Cutting Edge KYOGEN 真夏の狂言大作戦 2023
【狂言 Cutting Edge 】


狂言 #茂山千五郎家 のご贔屓5人 千五郎、宗彦、茂、逸平、千之丞の「Cutting Edge KYOGEN 真夏の狂言大作戦 2023 狂言 de 落語」を観に、西宮 阪急ホール。
1部は、落語「#犬の目」と「#粗忽長屋」をうまくつないで狂言仕立てにした舞台。宗彦はほんとに出てくるだけで花があり、動くたびに会場は笑いにつつまれる。毎度のことながら、千五郎の声には惚れ惚れ。
しかし、よくもこんなふうに書けるもんだと千之丞の才が妬ましいほど。
2部は、落語「#たちぎれ線香」。最初の部分はヒャクマンベンを彷彿させる黒子のダンスで笑わせておきながら、この黒子が次々と変化しながら場をもりたて、若旦那の逸平、番頭の千五郎、女将の茂がその中で狂言。
後半の茂と逸平の女将と若旦那のやりとりは、ふざけた部分は封印し米朝落語そのものの台詞だてで、会場が涙涙となる。
一瞬しかでないが、何よりだいじな幽霊となった小糸の地唄「雪」のお三味と唄も本物。伝統芸能と演劇とコントを駆使し、狂言をしらないひとにも伝わる工夫があふれる。
開演ぎりぎりまで、逸平、茂がclub soja のTシャツ売り場にいるサービス。帰りは、全員でのお見送りが再開。
ああコロナ終わったんだなと、つくづく思う。









2023年07月07日
風姿花伝 難しかったぁ
【風姿花伝】
10月21日に #宇多津圓通寺 で盆点前ガールズとやろうとおもっている音楽と言葉と茶会「#風姿花伝(仮)」の原稿ようやく脱稿。
難しかった!
芸事だけじゃなく、なにかを成すためには超えないといけないことがたくさんある。
観阿弥世阿弥の親子が「能」の奥義をまとめ上げるまで、いかに真剣に生きたかがビシビシ伝わってくる本だった。600年前の思想とは思えない。
漫然と日々を過ごすのは安全だが、#ただ真面目だけでは何も成せない。伝統も守って行けない。ましてや戦国の世を生き抜いてはいけない。
世阿弥は、少年時代から足利義満の寵愛をうけている。圓通寺を居館としていた細川頼之は義満とのご縁が深い。圓通寺で初演を迎えるのは正しいルートだ。
「秘すれば花」
なんでも手のうちを見せていたのでは戦いに負ける。いかにしんどい思いをしていても平気な顔でいなければならない。
500年秘伝として一子相伝とされた風姿花伝は20世紀になってから一般のひとに読まれるようになり、芸能だけではなく、経済界のトップが競って読み経営の書とした。
大いなる発想と、変化しながら新しいものをつくる力、そしてそのたびに初心を我が身にといながら進みゆく謙虚さをもつひとが、自分自身に打ち勝つひとかもしれないね。
班長92(母)の薬をもらいにきたので、ついでに血圧を測ってみた。
やはり、徹夜が続くと血圧低め。早く用事すまして昼寝しよ。

2023年04月10日
安田さん、うまいこと書くな(笑)
朝から、能楽師 安田登さんのTweetに、「うひひ、そうだ そうだ」と思う。
何かとわかったようにいうひとは、釈迦のいう無意識の悪意なんだと私はおもってるよ(笑)
しかし、安田さん、うまいこと書くな。
「毎回そうですが、下書きもせず、見直しもせずに送っちゃうので、RTとかされて再び目にすると誤字脱字にたくさん気づく。でも、Twitterなどでそんなことを気にするようになったら、窮屈なので(あまり)気にせずバンバン行きます。」
そうそう、バンバンいってください。
…………………安田登さんのTwitterから
ビジネス関係の人と飲むと、こちらがお願いしていないので教えようとする人がいて「能も歌舞伎のようにもっと現代的にして、CMなども打てばお客がたくさん入るのに」なんていう。相手はだいたい酔っぱらっているので(そうでなくても)「はいはい」と黙って聞いていますが、頭の中では次のように反論→
→しているので気を付けるように(笑)
①歌舞伎は松竹という企業。能は個人。だからこその自由さがある。
②国立能楽堂ですら600席。客をそんなに呼ぶ必要はない。
③もっと大きな席が定席になると能面の微妙は表情などが見えず、かつての浪曲と同じ失敗を招く。
④能も企業経営になると大衆の好み→
→に合わせるようになる。そのひとつが「家柄主義」。日本の大衆は家柄に弱い(笑)。能でも宗家・家元は大切ですが、しかしその家の人でなくてもいろいろできる。そういう自由さもなくなる。
⑤てなわけで能にマーケティングなんて冗談じゃねぇ!
…と頭の中で反論しています。
………………
とはいえ、狂言 茂山千五郎家の若手が作る Cutting Edgeは満席になってほしい。
8/26(土)「Cutting Edge KYOGEN 真夏の狂言大作戦2023」
いよいよ明日【4/7(金)10:00~】会員先行予約開始!
今年の夏もCEKが芸術文化センターでハジけます!
最先端狂言でめくるめくCEKワールドへお連れしましょう。
今年は兵庫公演のみ。8月最後の週末はみんな芸文へ集合!

2023年03月13日
老人90(母)絶好調!(笑)
【元気です】
るいちゃ社長(娘)と老人90(母)に江戸土産と京土産を運ぶ。
とにかく喋る喋る。とどまることを知らないノンブレストークは健在(笑)
話に夢中になり中腰前のめりショット
もおさえとく。



【弾丸帰省おしまい】
京都で狂言みてギアみて、老人90(母)の面会に行って、頼まれたものを買って、名前書いたり準備したり、その合間にリモートでどんどん仕事をしていた2日間がおわり、るいちゃ社長 お江戸へ。
お疲れさん♪
仕事もあるし、猫もいるし、なかなかゆっくり出かけられない私たちではあるけど、おばあちゃんも含め、ときどき会うようにしようじゃないかと話す。
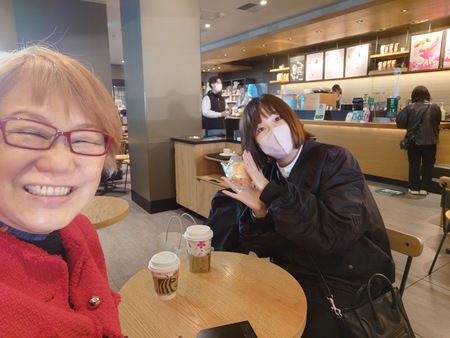
るいちゃ社長(娘)と老人90(母)に江戸土産と京土産を運ぶ。
とにかく喋る喋る。とどまることを知らないノンブレストークは健在(笑)
話に夢中になり中腰前のめりショット
もおさえとく。



【弾丸帰省おしまい】
京都で狂言みてギアみて、老人90(母)の面会に行って、頼まれたものを買って、名前書いたり準備したり、その合間にリモートでどんどん仕事をしていた2日間がおわり、るいちゃ社長 お江戸へ。
お疲れさん♪
仕事もあるし、猫もいるし、なかなかゆっくり出かけられない私たちではあるけど、おばあちゃんも含め、ときどき会うようにしようじゃないかと話す。
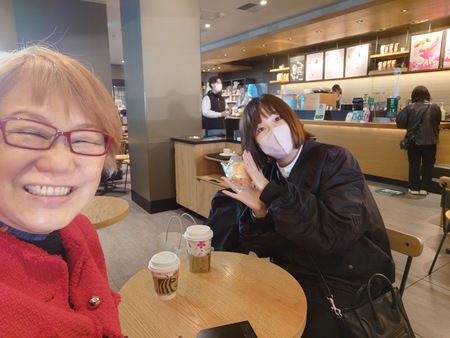
2023年03月13日
またも京都さんぽに参りました(笑)
【またも京都さんぽに参りました】
3月12日(日)快晴。京都さんぽに参りました。
もはや、京都が空いているなんていうのは幻想。日曜日のお昼時ってこともあって京都駅はひとだらけ、観光バスを待つ人の行列も。
今日は、大江能楽堂のある烏丸御池まで歩く予定。片道3.5kmほどの、さんぽにぴったりのコース。



【牛たん伊之助】
東京から帰省途中の るいちゃ社長(娘)と京都駅で合流。
「京都のごはんは並ぶ」は、前回、前々回の京都さんぽで思い知っているので、まずは #牛たん伊之助 でしっかり肉をくらう。るいちゃ社長との旅で嬉しいのは、腹ペコ度合いが似ているので、ちゃんとごはんが食べられること。「もう食べられない」って言いながらスイーツとかでごまかす女子旅は、私たちには無用(笑)
京都らしいのらしくないのは関係なく「炭火焼き牛たんと牛ロースの定食」。

【花子】
京都・東本願寺御影堂門前まで歩くと、横たわる巨大なこけし。
現代アートユニット「Yotta(よた)」によるもので、2011年に制作された「花子」。こけしの素材はテントなどに使われる生地でバルーンになっております。
身長約12メートル。美術館などは立って展示されたときもありますが、往来の東本願寺前では、あえて寝像。
時々「春がすぐそこ」「おやすみ」「ゆっくり」「ねむくなってきたよ」などと話すと聞いておりましたが、話し方が不気味で、なにを話しかけられたかは、わからぬまま花子とはお別れ(笑)
花子の東本願寺前の展示は、この日(3/2)が最後。


【マリコウジ in 大江能楽堂】
本日のメインイベントは、贔屓の茂山千五郎家、茂山童司(茂山千之丞)による新作狂言マリコウジ。千五郎家の長老たちによる古典狂言「長光」のあと、新作「瓜貝争い」と「山竦み(さんすくみ)」。狂言ならではの言葉の応酬の妙。よくぞ、このややこしいセリフを間違わずに言うもんだと思いながら笑う笑う。
大江能楽堂は、建物見学だけだも貴重な造り。1908年(明41)創建。金丸座同様、自然光による舞台。昔は桟敷席にもたくさんひとを入れていたと思うのですが、現代の私たちは、桟敷に一列という贅沢な座りで、足を伸ばしての観劇。狂言を観るのははじめての るいちゃ社長もげらげら笑い、大満足の90分!
これについては、また別の記事をたてます。


【河道屋】
大江能楽堂をでて、本日二本目の観劇となるギアの専用劇場に向かう途中。
京都三代老舗高級旅館「俵屋」「柊屋」「炭屋」のある麩屋町通りへ。
「俵屋」は300年の歴史を持つ老舗中の老舗。スティーブ・ジョブズが日本に訪れたときの京都の定宿。もちろん雑誌で見ただけですが、なにもかもがおしゃれ。
「柊屋」は1818年創業。川端康成や三島由紀夫にも愛された旅館。
その麩屋町通りにあるのが、蕎麦「河道屋」
「弊舗の祖先はもと桓武天皇の平安京遷都と共に随って移り住み元禄の頃には上京の小川通上長者町上る処に店を構えて菓子を商う旁ら河漏(そば)を商っておりました・・・連綿16代」。
と、河道屋のwebにありますから、こちらも3つの老舗旅館に負けず劣らずの歴史をもつお蕎麦屋さん。
時間は、まだおやつどきの4時前ながら、「食べたいものは食べておこう!」の腹ペコふたりは、鰊蕎麦と筍ごはんをいただく。
帰りに、河道屋の蕎麦ほうる(そばぼうろ)を買う。






【ギア専用劇場 同時代ギャラリー】
ギア専用劇場のことは、この近くにある京都文化博物館に来たときに地図でみて知っていたようなきがするんだけど、私にはあんまり関係ないものだろうとスルー。
今回は、るいちゃ社長も一緒だし、ちょっと覗いてみるかとチケットをネットで購入。その上、50歳オーバーは1000円プライスダウン(笑)
ところが会場に着いてみると、びっくり。すごかったから!
これについても別に記事を書きますが、ほんとに「騙されたと思って一度いってみるべき」身体表現と舞台装置とマイムとダンスとマジックで進むステージは息つく暇もない展開。セリフがないがゆえに、外国のお客様が客席の半分近くを占めているのに、ぜんぜん取りこぼされていない。
私たちの隣のマダム3人は、何回も何回も、このステージを観ているようで、のり方が尋常じゃない(笑)何より10年間も公演を続けているのに、ほぼほぼ満席で、今回もあっという間にチケットがなくなっておりました。
全パフォーマーの紹介の中には、マイムのいいむろなおき さんの名前もあり、私が観た回のマイムは、どこかのタイミングで必ず舞台を観ようと思っている劇団「壱撃屋」の代表大熊隆太郎。ドールは河瀨直美監督の映画「沙羅双樹」の主演女優兵頭祐香。
ちなみに、いいむろなおきさんは、パリ市マルセル・マルソー国際マイム学院卒業後、ニデルメイエ国立音楽院コンテンポラリーダンス科最上級クラスを首席卒業という、まぎれもなく日本のマイムの第一人者。
村山岳の出演した、ダンス・インキュベーション・フィールド岡山で観て「すごいね!あのマイム」と言った記憶も新しい。




【ただいま高松】
今回の「京都さんぽ」は、狂言マリコウジを観る目的だったんだけど、るいちゃ社長といくことになって、ギアも観ようとなったおかげで、もうひとつの京都の魅力と底力を見た感じ。
高松駅から、また歩いたので16kmになっているけど、今回の京都は13km程度のさんぽ。わりと素直な行程だったので、迷うこともなく、お腹を空かすこともなく、22時には高松に到着。


・・・・・・・・・・・・
その他
【京都昼さんぽ】
■紙司 柿本

https://www.kamiji-kakimoto.jp/
紙司柿本の起源は、享保年間(1716)に遡ります。
当初は竹屋が軒を連ねる京都・寺町二条の地で「竹屋長兵衛」の屋号で代々竹屋を営んでいました。
やがて若狭の親戚から長兵衛のもとへ養子として金蔵が迎えられました。
金蔵は斬新な発想の持ち主で、
「町内みんなで竹屋をしていても知恵がない」と1845年に紙屋を創業。
その進取の気性は、2代目乙五郎、3代目藤治郎、4代目新太郎、当代新也と受け継がれていきます。
「柿本」が積み重ねてきた足跡は和紙から洋紙、紙製品へと紙の可能性を追求する歴史でもありました。
■京都国際マンガミュージアム


(きょうとこくさいマンガミュージアム、Kyoto International Manga Museum)は京都市中京区の旧・龍池小学校跡地にある日本最大の漫画博物館である。
国内外の漫画に関する貴重な資料を集める日本初の総合的な漫画ミュージアムとして2006年11月25日に開館した。明治時代の雑誌や戦後の貸本などの貴重な歴史資料、現代の人気作品、世界各国の名作など約30万点(2011年現在)を所蔵している。
マンガ学部を持つ京都精華大学と土地・建物を提供した京都市によって共同事業として整備が進められたもので、現在は市と大学で組織される運営委員会の下、大学が管理・運営している。
近世思想史や美術史などを専攻する研究員4人が所属し、まんが文化の研究にあたっている。
施設は廃校になった旧・龍池小学校の校舎を改築(一部増築)して利用している。旧・龍池小学校の本館・講堂・北校舎・正門および塀だった建物は2008年7月23日に国の登録有形文化財に登録された。
■本屋ともひさし

https://www.mishimaga.com/books/hajimemashita/004193.html






