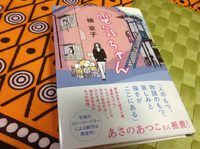2011年08月13日
大野更紗「困ってるひと」読了。目を背けない生き方。
お盆13日 今日は、るいまま組@マイトさんのお誕生日であります。
(おれは、るいまま組ちゃう!っていうつっこみお待ちしてますw)
さて、怒濤のまちかど漫遊帖2011秋編の
ガイドブック制作も佳境にはいり、
デザイナーのイチリちゃんは仕事をしつづけているというのに
わたしは、やるべき取材は終えたし、ざっくり資料は渡したしと
まだ、自分が書かないかん大きな頁があるのに、夕べは石あかりロードの原稿をかき
そのあと、amazonさまから届いた本をよみながら就寝。
今朝、蝉時雨のなか、扇風機ひとつの暑い暑いへやに寝転んで、本のつづきを読んだ。
ああ、この体勢は、中学校の夏休みだな。

外で遊ぶなどという子どもっぽいことに否定的で、人と交われば自分の弱点をさらすことになり
そんなめんどうな社会になどでないでおこうと、ひたすら部屋のなかで読み続ける本。
本を存分に買うという資源もなく、父の書棚からとりだしてきた、中学生は絶対読まないような本ばかりだから
当然にして、中学生としての社会性はどんどん損なわれ、孤独のなかに自分からはいりこむ。
西側の子ども部屋は、大人がはいってくることをこばみカギをつけたのに
モンスターのようなばばさまが、力ずくでカギをこわして、まっとうな話ばっかりする。
まっとうで、きちんとしてて、ばばさまの道理にかなう話が、いつの世も正しいと思うな!
けれど、子どもは無力だ。
いつだって、大人に逆らえば、今日を生きることも出来ない。
なんて、子どもは不幸なんだろう。
大野更紗「困っているひと」を読みながら、わたしは、そんな自分を思い出していた。
彼女は1984年生まれの26歳。
福島の田舎町から上京し、上智大学外国語学部フランス語学科を卒業し
その間に、ビルマ(ミヤンマー)難民の民主化運動や人権問題に出会い
絶対的な活動力で、現地取材や支援活動をしていた。
2008年、大学院に進学した年、原因不明の発熱と激痛が彼女を襲い
体の筋肉、関節、皮膚、その他もろもろのものが連鎖的に崩れゆく中
1年間の想像を絶する検査と、病院行脚を繰り返し、
自己免疫疾患系の難病「筋膜炎脂肪識炎症候群」と診断され
治療方法も手探り状態のなか、現在も、副作用と戦い、現実と戦い
「難」とともに生きている。
まことに軽快な文章、いまどきのコピー、そして何より、たくましき精神が
読者をぐんぐん引っ張っていく。
人が「生きたい」、明日も「生きよう」って思うことは、大上段にかまえたりっぱな理由よりも
もっともっと身近に思えるものであり、それを甘く見ちゃいかんよと、
平成の子どもは言う。
amazonの書評のなかに、結局彼女は自分が悪者にならないようにして、自分のことをかき
こっちを見てといっているだけだというものがあった。
「こっちを見て、わたしをみて!」で、何が悪い?
と、わたしは思う。
自分の思いは、自分でしか書けない。
人に伝える文章に整理することはできても、ほんとに伝える思いは自分で書くしかない。
他人になにかを言われるとわかっていても、書き、それを発信するまでに
多くは「みられる自分」に恐れおののき、心折れてしまうことも多いのだ。
この本のなかで彼女は自分の難病を隠さないと言い切る。
どう見られるかの前に、生きるためには、いかにすればよいかを考える。
ここから教えられたことはほかにもある。
まず、なんとなくぼんやりとはわかっているつもりだった「難病」と言われる病を抱えるひとたちの日常。
それをとりまく社会。医療。行政。
そして、「難」を抱えるひとたちの、物言わぬ現実。
知らないがゆえに、仕方ないというよりも、
自分とは関係のないことだからと、見ようともしないままでいたような気がする。
「困っているひと」が上梓されたあと、東日本大震災がおきている。
たぶん、わたしは、ZENKON湯の仲間と出会っていなければ、
通り一遍のチャリティー活動をしたあと、今頃は、現実をみることも忘れて別のことで走り回っていた。
大野更紗は、「難」と戦うため薬の副作用でお月さまのように腫れた体でありながら
すでに現実に立ち向かっている。
冷静に、着実に、社会を見つめる。
大野更紗の名前は、NPO「自殺対策支援センターライフリンク」の企画
連続対談「メメント・モリ(死を憶え)」で知った。
http://news.nicovideo.jp/watch/nw96067
「メメント・モリ」とは、
ラテン語で「死を憶(おも)え」、「喪失を忘れるな」という意味の言葉。
就職に失敗したり、病気になったり、大切な人を亡くしたり。
生きていれば誰しもが、そうした「喪失」を体験するものです。
でも、いったい「喪失体験」とどう向き合っていけばいいのでしょうか。
忘れるまで耐えるのか、ポジティブな発想に切り替えるのか、
それとも喪失の意味をジックリ思考するのか。
この対談のなかで、彼女は言う
「誰だって生きていれば、その中で何らかの『クジ』を引くわけですよね」と人生で出会う不条理をクジ引きにたとえる。
「それが何のクジか分からない。被災するクジかもしれないし、失業したり、いじめに遭ったり・・・。
いろんな社会問題があって、みんなが困っている。みんなが閉塞感を感じている」
「テレビとかで被災者に『お気持ちは』と聞くじゃないですか。
でも、例えば、私の場合、病室に急に来られて『お気持ちは』と聞かれても、何て答えれば良いんだろうと。
『大丈夫です』とか『ありがたい』とか言うしかないんですよね」
かわいそうがったり、悲惨だと涙するのは、実は一番簡単なことで
その時点で、受け取る側は完結できる。
けれど、ほんとに大事なのは、知り得たことに、いかに目をそむけず生きるか。
中学生のころ、わたしは現実から目を背けることで自分を守ろうとした。
本を読むことも、小説を書くことも、その延長線上にあったように思う。
けれど、そのなかから生まれたのは救いではなく閉塞感ばかりだった。
現実を生きようと一度ペンを置いた。
いまの私は、ちゃんと「目を背けない生き方」ができているだろうか・・・
(おれは、るいまま組ちゃう!っていうつっこみお待ちしてますw)
さて、怒濤のまちかど漫遊帖2011秋編の
ガイドブック制作も佳境にはいり、
デザイナーのイチリちゃんは仕事をしつづけているというのに
わたしは、やるべき取材は終えたし、ざっくり資料は渡したしと
まだ、自分が書かないかん大きな頁があるのに、夕べは石あかりロードの原稿をかき
そのあと、amazonさまから届いた本をよみながら就寝。
今朝、蝉時雨のなか、扇風機ひとつの暑い暑いへやに寝転んで、本のつづきを読んだ。
ああ、この体勢は、中学校の夏休みだな。

外で遊ぶなどという子どもっぽいことに否定的で、人と交われば自分の弱点をさらすことになり
そんなめんどうな社会になどでないでおこうと、ひたすら部屋のなかで読み続ける本。
本を存分に買うという資源もなく、父の書棚からとりだしてきた、中学生は絶対読まないような本ばかりだから
当然にして、中学生としての社会性はどんどん損なわれ、孤独のなかに自分からはいりこむ。
西側の子ども部屋は、大人がはいってくることをこばみカギをつけたのに
モンスターのようなばばさまが、力ずくでカギをこわして、まっとうな話ばっかりする。
まっとうで、きちんとしてて、ばばさまの道理にかなう話が、いつの世も正しいと思うな!
けれど、子どもは無力だ。
いつだって、大人に逆らえば、今日を生きることも出来ない。
なんて、子どもは不幸なんだろう。
大野更紗「困っているひと」を読みながら、わたしは、そんな自分を思い出していた。
彼女は1984年生まれの26歳。
福島の田舎町から上京し、上智大学外国語学部フランス語学科を卒業し
その間に、ビルマ(ミヤンマー)難民の民主化運動や人権問題に出会い
絶対的な活動力で、現地取材や支援活動をしていた。
2008年、大学院に進学した年、原因不明の発熱と激痛が彼女を襲い
体の筋肉、関節、皮膚、その他もろもろのものが連鎖的に崩れゆく中
1年間の想像を絶する検査と、病院行脚を繰り返し、
自己免疫疾患系の難病「筋膜炎脂肪識炎症候群」と診断され
治療方法も手探り状態のなか、現在も、副作用と戦い、現実と戦い
「難」とともに生きている。
まことに軽快な文章、いまどきのコピー、そして何より、たくましき精神が
読者をぐんぐん引っ張っていく。
人が「生きたい」、明日も「生きよう」って思うことは、大上段にかまえたりっぱな理由よりも
もっともっと身近に思えるものであり、それを甘く見ちゃいかんよと、
平成の子どもは言う。
amazonの書評のなかに、結局彼女は自分が悪者にならないようにして、自分のことをかき
こっちを見てといっているだけだというものがあった。
「こっちを見て、わたしをみて!」で、何が悪い?
と、わたしは思う。
自分の思いは、自分でしか書けない。
人に伝える文章に整理することはできても、ほんとに伝える思いは自分で書くしかない。
他人になにかを言われるとわかっていても、書き、それを発信するまでに
多くは「みられる自分」に恐れおののき、心折れてしまうことも多いのだ。
この本のなかで彼女は自分の難病を隠さないと言い切る。
どう見られるかの前に、生きるためには、いかにすればよいかを考える。
ここから教えられたことはほかにもある。
まず、なんとなくぼんやりとはわかっているつもりだった「難病」と言われる病を抱えるひとたちの日常。
それをとりまく社会。医療。行政。
そして、「難」を抱えるひとたちの、物言わぬ現実。
知らないがゆえに、仕方ないというよりも、
自分とは関係のないことだからと、見ようともしないままでいたような気がする。
「困っているひと」が上梓されたあと、東日本大震災がおきている。
たぶん、わたしは、ZENKON湯の仲間と出会っていなければ、
通り一遍のチャリティー活動をしたあと、今頃は、現実をみることも忘れて別のことで走り回っていた。
大野更紗は、「難」と戦うため薬の副作用でお月さまのように腫れた体でありながら
すでに現実に立ち向かっている。
冷静に、着実に、社会を見つめる。
大野更紗の名前は、NPO「自殺対策支援センターライフリンク」の企画
連続対談「メメント・モリ(死を憶え)」で知った。
http://news.nicovideo.jp/watch/nw96067
「メメント・モリ」とは、
ラテン語で「死を憶(おも)え」、「喪失を忘れるな」という意味の言葉。
就職に失敗したり、病気になったり、大切な人を亡くしたり。
生きていれば誰しもが、そうした「喪失」を体験するものです。
でも、いったい「喪失体験」とどう向き合っていけばいいのでしょうか。
忘れるまで耐えるのか、ポジティブな発想に切り替えるのか、
それとも喪失の意味をジックリ思考するのか。
この対談のなかで、彼女は言う
「誰だって生きていれば、その中で何らかの『クジ』を引くわけですよね」と人生で出会う不条理をクジ引きにたとえる。
「それが何のクジか分からない。被災するクジかもしれないし、失業したり、いじめに遭ったり・・・。
いろんな社会問題があって、みんなが困っている。みんなが閉塞感を感じている」
「テレビとかで被災者に『お気持ちは』と聞くじゃないですか。
でも、例えば、私の場合、病室に急に来られて『お気持ちは』と聞かれても、何て答えれば良いんだろうと。
『大丈夫です』とか『ありがたい』とか言うしかないんですよね」
かわいそうがったり、悲惨だと涙するのは、実は一番簡単なことで
その時点で、受け取る側は完結できる。
けれど、ほんとに大事なのは、知り得たことに、いかに目をそむけず生きるか。
中学生のころ、わたしは現実から目を背けることで自分を守ろうとした。
本を読むことも、小説を書くことも、その延長線上にあったように思う。
けれど、そのなかから生まれたのは救いではなく閉塞感ばかりだった。
現実を生きようと一度ペンを置いた。
いまの私は、ちゃんと「目を背けない生き方」ができているだろうか・・・
Posted by るいまま at 13:59│Comments(3)
│■音楽と言葉
この記事へのコメント
記事を読みながら
百回くらいうなずいたので首が痛くなっちゃいました(笑)。
今必要なのは、良い悪いではなく、
たまたま見えてしまったものに目をそむけず、
果敢に挑戦することですね!
私も「いい事」って何だ???なんて考えたこともないけど、
困ってる人がいて、アイデアが浮かんだら、周囲に関係なくやればいいと思います。
るいままさんは十分できていると思いますよ。
目は二つしかなんだから!!
百回くらいうなずいたので首が痛くなっちゃいました(笑)。
今必要なのは、良い悪いではなく、
たまたま見えてしまったものに目をそむけず、
果敢に挑戦することですね!
私も「いい事」って何だ???なんて考えたこともないけど、
困ってる人がいて、アイデアが浮かんだら、周囲に関係なくやればいいと思います。
るいままさんは十分できていると思いますよ。
目は二つしかなんだから!!
Posted by 0-た at 2011年08月13日 15:29
at 2011年08月13日 15:29
 at 2011年08月13日 15:29
at 2011年08月13日 15:29見えているのに見えないふりをする。自分はそうではないと思っていても、無意識にやっていたことに、あとで気が付きます。
Posted by 毎日聴いてる香川県人(HOSOSACHI) at 2011年08月14日 10:26
■おーた
ありがとうございます。
ほんまに、まず動いてみること大事ですね。
■hososachi
あるんだよね・・・。反省してる。
ありがとうございます。
ほんまに、まず動いてみること大事ですね。
■hososachi
あるんだよね・・・。反省してる。
Posted by るいまま at 2011年08月16日 20:58
at 2011年08月16日 20:58
 at 2011年08月16日 20:58
at 2011年08月16日 20:58※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。