2009年08月03日
津軽三味線 浅野祥
8月23日にトリートホールである津軽三味線の「浅野祥」くんのライブで、
るいまま&浅野祥のトークショーをとのお話になりまして、浅野くんに関してほとんど無知な私のために
浅野くんのマネージャーさんからDVDがたくさん送られてきまして、昼から、ずっと見続けておりますが
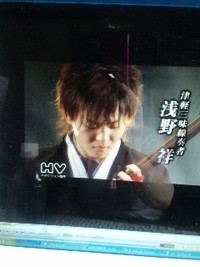
見れば見るほど、最初にもっていた
津軽三味線全国大会で三連覇し殿堂入りした17才の津軽三味線奏者。
細面の女の子のような容姿をもつアイドル。
という、イメージは、捨てなくてはなと思ったのでした。
彼が三味線を始めたのは5才のとき、民謡の師匠であるおじいちゃん(穣さん)の手ほどきでした。
練習がいやで、三味線の絃きったりする祥くんに、おじいちゃんは
「稽古は、一日5分でいいから」と導いていきます。
やがて8才で史上最年少の日本一をとり、あとはランクを上げながら全国連覇を重ね、
2007年A級の三連覇を果たし殿堂入りするのでした。
津軽三味線界のスターである吉田兄弟が、
少年浅野祥をみて、同じ年齢のころの自分たちは、ただ弾くと言う感じであったが、
浅野くんは、そのころから、すでに基本がものすごくしっかりしていたと言い、
「基礎のないところに、テクニックはない」と、繰り返しています。
津軽三味線は、感性とテクニックが問われるもので、JAZZのように奏法を組み合わせて
どれだけ即興で演奏できるかが大事とのこと。
だから、単に感性だけでも、テクニックだけでも成り立たないのです。
浅野祥くんの育った環境は、おじいちゃんが民謡の先生という土壌はあったものの
祖父の穣さんは、幼い彼に強いることよりも
「5分でいいから」と続けることの大事さを教えています。
芸事はやめてしまえば、そこで止まる。それまでの努力も、そこで途絶える。
早くに頭角を現した子こそ、持続させるのは難しいというのは、子ども落語塾をはじめたとき
師匠から聞いた言葉です。
だから、穣さんが民謡の師匠であったからというよりも、穣さんの人柄が彼を育んだはずで、
穣さんが亡くなったあとは、三味線は全く弾けない普通のサラリーマンのお父さんが
しっかりと精神面のサポートをしていて、
そうした環境が「心」をそだてたのだろうなと思い、
結局は、人は人が育てるのであって、人なきところに「心も技術も備わった天才」は育たないような気もします。
それには、本人の気質というのも絶対あるはずで
テレビ番組の中では、美しく清らかな高音を得意とする浅野祥のイメージをクローズアップするために
大きな挫折や、血のにじむような努力というのは消し去っていましたが、それが全くない人間などおらず、
挫折のとき、荒れたとき、救われる言葉があるかないか
それを自らキャッチできるかどうかで、その先々は変わってゆくはずです。

穣さんは、亡くなるまえ、祥くんに、必ずプロになるように言っていますが、
「お客さんに感動してもらい、もう一回聴きたいと思う三味線を弾いてくれ」
と、言い残しています。
見た目のとおり、男っぽいというイメージとは遠く
父・俊さんは、「三味線を弾いていないときは、むしろ普通の18才よりも幼いかも知れない」と語りますが、
お母さんが話す、「決めたことを貫く力は、親でも勝てない」が、浅野祥を作り上げたのでしょう。
浅野祥くんが所属する、小田島流の師匠が
浅野祥は「自分の気持ちを三味線を借りて表現する」奏者というとおり
現代風外見だけで理解してはいけない、内証の部分を彼の演奏の中に見られるようになれば
浅野祥が、もっともっと理解できるのかもしれません。

■いみじくも夕べ、カワイさんやminoさんと、プロ・アマについて話していて
JAZZの山下洋輔が「アマだってすごいフレーズは演奏できる、でも、それは10秒なんだ」といったそうで、
「小説の世界も、人間は一生に1本すごい小説を書けるくらいのストーリーはみんなもっている。でも、
同じレベルで書き続けられるかどうかが、プロとアマのちがい」
と、私も教えられたことがあると話していて
どんな世界でも、プロになるには、瞬発的な10秒力を発揮できることよりも、
もっと地道がものが必要だと話したところでした。
■「浅野祥を評価するのは、もはや審査員ではない」
吉田兄弟のこの言葉は、これからプロの道に旅立つ後輩へのエールであると、私は思います。
*****************

こちら、祥くんが民謡の唄を習いにいった先生。えらい男前で(w
おじいちゃんの唄をきいて育った祥くんは、みずから唄を学ぶことで、リズム感や間合いを確かめるそうです。
memo>>
津軽じょんから節は、明治のはじめ頃、「おさまさん」と言われる盲目の三味線弾きのひとたちが
即興で唄と三味線を披露してまわったもので
そこには厳しい自然のなかで暮らすひとたちの魂の声があった。
つまり「自分だけのじょんから節」だ。
これって、やっぱり、サルサの原点ソンや、フラメンコのカンテに似てますねぇ。
音楽の原点は、ここにあるんだろうな。
るいまま&浅野祥のトークショーをとのお話になりまして、浅野くんに関してほとんど無知な私のために
浅野くんのマネージャーさんからDVDがたくさん送られてきまして、昼から、ずっと見続けておりますが
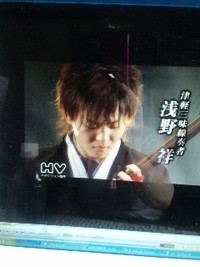
見れば見るほど、最初にもっていた
津軽三味線全国大会で三連覇し殿堂入りした17才の津軽三味線奏者。
細面の女の子のような容姿をもつアイドル。
という、イメージは、捨てなくてはなと思ったのでした。
彼が三味線を始めたのは5才のとき、民謡の師匠であるおじいちゃん(穣さん)の手ほどきでした。
練習がいやで、三味線の絃きったりする祥くんに、おじいちゃんは
「稽古は、一日5分でいいから」と導いていきます。
やがて8才で史上最年少の日本一をとり、あとはランクを上げながら全国連覇を重ね、
2007年A級の三連覇を果たし殿堂入りするのでした。
津軽三味線界のスターである吉田兄弟が、
少年浅野祥をみて、同じ年齢のころの自分たちは、ただ弾くと言う感じであったが、
浅野くんは、そのころから、すでに基本がものすごくしっかりしていたと言い、
「基礎のないところに、テクニックはない」と、繰り返しています。
津軽三味線は、感性とテクニックが問われるもので、JAZZのように奏法を組み合わせて
どれだけ即興で演奏できるかが大事とのこと。
だから、単に感性だけでも、テクニックだけでも成り立たないのです。
浅野祥くんの育った環境は、おじいちゃんが民謡の先生という土壌はあったものの
祖父の穣さんは、幼い彼に強いることよりも
「5分でいいから」と続けることの大事さを教えています。
芸事はやめてしまえば、そこで止まる。それまでの努力も、そこで途絶える。
早くに頭角を現した子こそ、持続させるのは難しいというのは、子ども落語塾をはじめたとき
師匠から聞いた言葉です。
だから、穣さんが民謡の師匠であったからというよりも、穣さんの人柄が彼を育んだはずで、
穣さんが亡くなったあとは、三味線は全く弾けない普通のサラリーマンのお父さんが
しっかりと精神面のサポートをしていて、
そうした環境が「心」をそだてたのだろうなと思い、
結局は、人は人が育てるのであって、人なきところに「心も技術も備わった天才」は育たないような気もします。
それには、本人の気質というのも絶対あるはずで
テレビ番組の中では、美しく清らかな高音を得意とする浅野祥のイメージをクローズアップするために
大きな挫折や、血のにじむような努力というのは消し去っていましたが、それが全くない人間などおらず、
挫折のとき、荒れたとき、救われる言葉があるかないか
それを自らキャッチできるかどうかで、その先々は変わってゆくはずです。

穣さんは、亡くなるまえ、祥くんに、必ずプロになるように言っていますが、
「お客さんに感動してもらい、もう一回聴きたいと思う三味線を弾いてくれ」
と、言い残しています。
見た目のとおり、男っぽいというイメージとは遠く
父・俊さんは、「三味線を弾いていないときは、むしろ普通の18才よりも幼いかも知れない」と語りますが、
お母さんが話す、「決めたことを貫く力は、親でも勝てない」が、浅野祥を作り上げたのでしょう。
浅野祥くんが所属する、小田島流の師匠が
浅野祥は「自分の気持ちを三味線を借りて表現する」奏者というとおり
現代風外見だけで理解してはいけない、内証の部分を彼の演奏の中に見られるようになれば
浅野祥が、もっともっと理解できるのかもしれません。

■いみじくも夕べ、カワイさんやminoさんと、プロ・アマについて話していて
JAZZの山下洋輔が「アマだってすごいフレーズは演奏できる、でも、それは10秒なんだ」といったそうで、
「小説の世界も、人間は一生に1本すごい小説を書けるくらいのストーリーはみんなもっている。でも、
同じレベルで書き続けられるかどうかが、プロとアマのちがい」
と、私も教えられたことがあると話していて
どんな世界でも、プロになるには、瞬発的な10秒力を発揮できることよりも、
もっと地道がものが必要だと話したところでした。
■「浅野祥を評価するのは、もはや審査員ではない」
吉田兄弟のこの言葉は、これからプロの道に旅立つ後輩へのエールであると、私は思います。
*****************

こちら、祥くんが民謡の唄を習いにいった先生。えらい男前で(w
おじいちゃんの唄をきいて育った祥くんは、みずから唄を学ぶことで、リズム感や間合いを確かめるそうです。
memo>>
津軽じょんから節は、明治のはじめ頃、「おさまさん」と言われる盲目の三味線弾きのひとたちが
即興で唄と三味線を披露してまわったもので
そこには厳しい自然のなかで暮らすひとたちの魂の声があった。
つまり「自分だけのじょんから節」だ。
これって、やっぱり、サルサの原点ソンや、フラメンコのカンテに似てますねぇ。
音楽の原点は、ここにあるんだろうな。
Posted by るいまま at 17:16│Comments(0)
│仕事
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。












