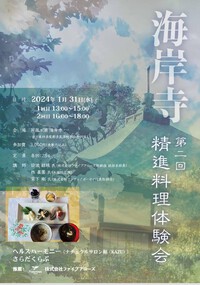2013年10月30日
丸亀本島 天気晴朗なり!
今年は気圧の変動が大きく、使いもんにならん三半規管を持つ身としては、
つねに船酔い気分の日がつづき、
これだけ瀬戸内国際芸術祭丸亀本島@とぐろ&咸臨丸押しなのに、
自身は島には渡れないなぁとあきらめていた10月30日。
二日つづきのお天気、風もつよくなく、ワタクシの三半規管もまぁまぁ良好。
この日を逃してはならんと、朝から丸亀。
無料駐車場は満車だったのに、このZENKONサコッシュのおかげか、車を置かせてもらえることになり

無事10:40のフェリーに乗船。
この日に意を決したのは、お天気以上に、前日、tameちゃん涼子ちゃんまで本島入りし
版築の作業を手伝ってくれてると知りまして、

ZENKONチームの私が、一回も土を打ってないんじゃいかんじゃないか!と。
丸亀本島港着岸!当然、まずはこれをみる。

石井章「出航」
この作品のモデルとなった咸臨丸は、洋式のスクリューを装備する船としては初の軍艦であり、
幕府の船として初めて太平洋を往復した。
その航海にあたり、塩飽諸島の水夫35人が乗船したと伝えられ、今もこうして名を残している。

海岸沿いに散策。




途中の家に、こんなこて絵のようなものがあった。新しいもののようだけど。
旗のたつところは、本島市民センター。
島は、夏生まれの猫が一番かわいい時を迎えていて、のどか。

「木烏(こがらす)神社の鳥居」
寛永4年(1627)に建てられたもので本島で最も古い石の鳥居。様式は明神鳥居。
当時の年寄宮本伝太夫道意の子半右衛門正信が建てたもので、
薩摩の石工である紀加兵衛の製作。

「年寄りの墓」
豊臣、徳川時代を通じて塩飽諸島を統治していた権力者「年寄り」の墓のひとつ。宮本家の墓。
宮本家、入江家、吉田家の墓は、勤番所と共に国の史跡に指定された。
丸亀本島@とぐろの煙突・・・・になるはずの支柱がみえてきました。

この日は、サイトーくん カワニシくんが作業中。

美しい版築の縞模様です。

屋根は船底をイメージして「むくり」になっている。横がそっているのは物理的な角度。
これを瓦で作ろうとすると雨漏りの原因となるので、今回はスレートで作られている。
版築の作業は、70cm×45cm×3m が普通の人の一日の作業でできる。
版築の縞模様を見ると、雨の多い日、晴れの日、上手く運んだ日、そうでもない日と
天候や気持ちの有り様が見えて来る。それが瀬戸内海の波のような縞模様となる。
塩飽大工と版築は関係ないようだが、大陸からここまで版築の技術は流れてきている。
版築は非常に頑丈で、城壁や墳墓などの大規模な建造物をはじめ、道路や家屋などにも用いられてきた。
版築は日を追うごとに硬くなる。とぐろが一番硬くなるのは300年後。
なにより覚えておきたいのは、
このたてものに使われている土は、とぐろの前の道路を整備したときにでた土。
何もないところからでも、いまそこにある材料で、建物はたてられるのだということ。
人間には、そういう力が潜在的に備わっていて、
大工や、建築家の技術や知恵をかりながら、建てていけるということ。

現在、2棟がほぼ完成していて、シャワー棟にはピンホールカメラが設置されている。
本来覗かれそうなシャワー室を、実は内側から覗くというしゃれっ気のある棟には、
島本親方の作った庵治石の小さな風呂も設置されている。
ピンホールカメラをのぞくと、瀬戸大橋や海が逆さにみえ、ゆっくり覗けば、それはどんどん広がる。
カメラの下の水盤は、立ち入り禁止と光の反射を目的にしている。
形ばかりお手伝い。

正直、瀬戸内芸術祭2013クローズまで数日、
私のようなものが少々手伝っても役にはたたないけど、気は心。
お昼は、港の屋台「しま家」
牡蠣のチーズ焼き、ローストビーフ、柳川丼、秋刀魚のお造り、たこの柔か煮。
どれもこれも美味し! ここで、こんなおごっつぉ食べられるとは!!






屋台とは思えぬ、きめ細かな調理。これはあなどれん!
2時から、笠島地区で堀川久子さんのパフォーマンスがあるときき、移動。


長い竿に弦を一本張り、ひょうたん状の一弦琴を弓と石でできたバチで弾き、
それに合わせて、堀川さんがかどづけのように、家々を回りながら踊る。
狂女のようでもあり、子どものようでもあり、見ごたえあり!(いい日に来たよ)


「国の重要伝統的建造物群保存地区・本島笠島地区」
本島の北側に位置する笠島地区。なまこ壁や格子窓が特徴的な、江戸時代、明治時代の古い街並み。
塩飽大工が建てた堅牢な建物が並んでいる。

こうした建築物を建てた塩飽大工衆のおひとり高島さん。
最後の大工衆であり、サイトーくんたちも高島さんから、いろいろなことを教えていただき、
今回の作業となった。


午前中は、お客様の対応に追われていたけれど、午後からは本格作業!
こうなったら、もう、私がちゃらちゃら手伝うことなどない、ものすごいスピード。
版築@とぐろは、続・塩飽大工衆の力によってどんどんできていく。
みんなの作業がはじまったところで、私は再び笠島にもどり、
瀬戸内芸術祭とは別だけれど、若手のアーティストさんたちがやっているアート展示をみてまわる。





カワニシくんが、サイトーくんの腕が、もはやプロレスラーと変わらない筋肉量になっていると言い、

考えれば、この人たちはは、3年前、東日本大震災から一か月もたたない4月のはじめ、
ZENKON湯として東北に走り出した日から、
アクセルを弱めることなく走り続けているなと、つくづく思う。

本島のみなさんに見送られ帰途についたのは、夕方5:10のフェリー。
頭はぐわんぐわんと揺れ始めたけれど、まぁ、それは数日すれば治ること。
Posted by るいまま at 22:00│Comments(0)
│■ZENKON-nex
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。