2021年04月23日
「関」そして 6月のこと【木曜日の茶室る庵 4/22 記録】
【木曜日の茶室る庵 4/22 記録】
今日は、盆点前ガールズが二人おやすみなので、お客様をとお声がけしたら、イタリアンの中野シェフが差し入れとともに来てくださり、稽古前にあれこれお話。

床にかけた「関」について話しながら、中野さんが料理人としてこえてきた「関」、茶人としての「関」について伺う。
仕事と茶の湯がリンクしたとき、ひとつなにかが広がったというお話は、いま私が思うことへのヒントになった。茶の湯が、自身の暮らしのどこにあるかは大きい。
かおりんが稽古にやってきて、まずは自分で着物を着る稽古から。どんな着物でもいいから、稽古のときは着物を着るようには、私が少女の頃、出稽古にきてくれていた大伯母から言われたことだ。

中野さんに、最近、気づいたのだけど、る庵の盆点前ガールズたちは所作が美しいんですよと話すと、中野さんが、「それはそうなると思います。着物を着て点前をすると、なぜここでこう動くのかがわかりましたから」と言い、
反発ばっかりしていたけれど、大伯母に教えられたことは無駄になってないなと思うばかりだ。
6月は古田織部が亡くなった月ゆえ、茶室る庵6月席は、織部について考えてみようと思い、パティスリースミダの住田社長をまたまた呼ぶ。
夕方、織部と話していたので住田さんなりの織部のイメージを話してくれ、面白いものになりそう。
貧乏茶室 茶室る庵に織部が揃うはずもないけれど、お菓子のテーマを緑に置きますってことで、じゃ、私も負けずに緑で行きますよなんて話していたら、洋子ちゃんが「苫米地さん いけるね(笑)」と言い、
正に正に、苫米地さんにはお目にかかったことはないけれど、こんなに役に立ってくださって、コロナがあけたら、一度個展に足を運びお礼を言いたいよと話す。
苫米地 正樹 の緑の茶碗は、去年、コロナで発表の場を失った作家さんたちの作品を、アバンギャルド茶会 の近藤さんが集め、webの展示会をしたとき求めたものだ。
数年後、コロナの年にはねと振り返るお話のきっかけにと思っていたが、苫米地さんのこのお茶碗は、胴絞りの形が冬には重宝し、クリスマスのときは赤い茶碗と合わせ、若葉の季節には山の緑に見立て、たぶん、茶室る庵の茶会で一番出動している。

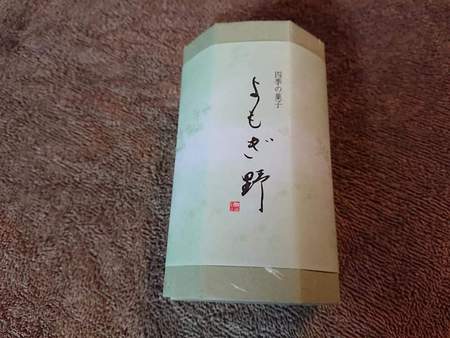
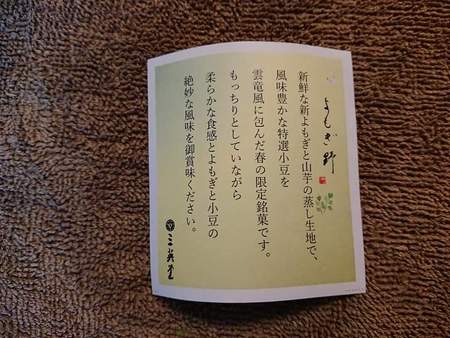


※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。













